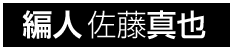PEOPLE インタビュー

林 恭三
やりたいと思った事は、何やってもいいんじゃないかなって
取材日:2004/12/17
中国育ちなのですよね?
1939年の名古屋生れですが、2、3歳で中国に渡ってしまったので、
名古屋の所在がどこかは覚えていないんです。父は華北鉄道の会社員でした。暮らしたのは北京の近くの長辛店という小さな町です。その町にはフランス人街があったのですが、日本軍が追い出しちゃったみたいでしたね。僕が住んでいたのは、中国の旧家の一角で煉瓦造りの家でした。親父、おふくろ、兄貴2人の家族5人で住んでいました。
冬はとても寒く、近くの川でスケートができたんですよ。中国で強烈に覚えているのは、青島に夜行列車で家族旅行した時の事です。何処まで行っても朝日がついてくるんですよ。走っても走っても。ずーっと地平線です。広い、とにかく広かった。
終戦は中国でむかえました。なんとか、翌年の4月に帰国しました。山口県の先崎に着くと桜が満開で、日本の町並みがあまりにきれいなのでびっくりしました。緑がもの凄く豊かできれい。水がきれい。風景がもの凄くきれい。…中国は暗い印象ではなかったのですが、灰色に近い雰囲気なんです。あまり、町に色がない。ですから、日本の桜の色を見たときは衝撃でしたね。
帰国後は名古屋に?
親父が繁華街で金物屋を始めたんです。でもそれは表の顔(笑)。金物を運ぶ貨車の中に米を積んで運んでいました。いわゆるヤミ米と呼ばれるものですね。家の石炭箱にはたくさんのお札が詰まっていましたね。兄は1枚抜いてもわからないだろうと、抜いては僕によく奢ってくれました。
でも当時は「飴長者」と言って、その更に上を行く人がいたんです。砂糖が配給制だったので、甘い物不足でした。僕が小学校2年の時に親父が飴工場をやると言い出しまして。芋がたくさん取れ、でんぷん工場があった伊良湖岬に移りました。でも買った機械がなかなかうまく動かなくて…。親父は試行錯誤していましたね。やっと飴ができるようになった時には、砂糖の配給制がなくなって……、みんな駄目になっちゃった。それは僕が小学校6年の時のことです。
学校の思い出はありますか?どんな少年時代だったのでしょう?
小学校頃、僕はなぜか絵のコンテストでは入賞していました。絵は抜群に上手かったんです。7歳頃その才能に気が付きました。特別に絵が好きではなかったんですが、俺って上手いんだなって(笑)。
中学校は名古屋に戻ったのですが、その頃も絵は好きでしたね。
いろいろあって親父が家を出てしまっていたので、僕はアルバイトで新聞配達をして家にお金を入れていましたね。おふくろは自転車で駄菓子売っていました。もう本当にどん底ですよ。それが中学、高校と続きましたね。
高校は工芸高校ということですが?
僕の行っていた工芸高校は、学校を出たらすぐ職人として使えるという学校ですね。変な学校で3分の1を実技・図案、3分の1を勉強、3分の1をファインアートに当てるんです。でもそこでは嘱望された記憶はないですね。僕は月謝を払わない、さぼってばかりいる。不良ではなかったんですが、最悪の生徒でした(笑)。
その頃、親父が家庭に戻って来て、家具屋を始めました。当時は物の無い時代ですから、家具は飛ぶように売れました。あっと言う間に会社が大きくなりましたね。親父が言うんですよ「働かなくて良い。食わしてやるから」って。だから、ずっとぼーっとして過ごしていました(笑)。
会社に入ってもすぐに辞めてしまったり、入社しても会社が潰れたりとなかなか長続きしなかったですね。東京に行ったり、名古屋に帰ったり…ブラブラしていた頃ですね。ある時、フォトグラファーの中村正也さんの事務所を紹介してもらったんです。中村さんと言えば、売れっ子でしてね。大変な勢いでした。事務所の中にデザイン室があり、そこに勤めました。1年以上はいましたね。
そこを、辞めてしまって、ブラブラしていると親父に「名古屋に帰って来い。食わしてやるから」と言われ実家に帰ったんです。一応フリーのイラストレーターということにはしていましてけれど、大きな仕事は無かったですね
ちょうどその頃、「東京イラストレーターズクラブ」というのができて、カットを出したら入選したんですよ。2年連続で入選して、イラストレーターズクラブの会員に推薦してもらいました。その頃から粘土で作った立体イラストレーションもやっていまして、68年の講談社のイラストレーター年鑑には立体の作品が掲載されています。それが、日本で初めて立体が載った年鑑だと思います。
立体でもイラストレーションと認められた一番初めという事ですか?
ええ。ただ当時はイラストレーションというのは平面で描くものだという固定概念がありました。デザイナーからも「これはイラストレーションか?」って聞かれる時代でしたね。その後、31歳で上京していたんですけど、仕送りしてもらっていました。その時はもう結婚していて、子供も2人いたんですけど。
80年代に入って、ダンボールを使った立体作品が流行して…。その頃ですかね、「イラストって何やってもいい」っていう自由な風潮がうまれたのは。雑誌『イラストレーション』が立体イラストレーションの先駆者ということで、何度か僕を取り上げてくれたんですね。それで順調に仕事が入ってくるようになりました。いやぁ、それからは目茶目茶忙しくなりました。
ただ、自分が売れてくると、まわりは不幸になったんです。僕が46歳の頃、おふくろが癌で亡くなりました。親父の会社が倒産して…。でも「今度は薬の会社をやるから金出せ」って言うんです。親父はその時70歳を越えていたんですけどね。結構、親父にたかられましたよ(笑)。その後、親父も兄貴も亡くなって…。僕だけ残ったんです。
ストーリーゲートの感想は何かお持ちですか?
『笑う星』(2005年公開予定)という僕の書き下ろしのストーリーをやることが決まった時は本当に嬉しかったですね。いろいろと想像しながら描いていますよ。
僕自身、絵本は大好きなんです。随分持っています。孫には随分読みましたね。多い時は1日10冊位読みました。でも、そのおかげで絵本のことが良くわかりました。ストーリー展開や絵に彼らがなんらかの親近感を持てばその絵本は持ちますね。その全体の雰囲気が子供の興味をひけば、絵本は成り立ちますね。
例えば僕が以前描いた古典落語をベースにした『あたま山』。友だちの子供に自閉症の子がいるんですけど、その子がこの本が大好きで。特に大好きなページがあるんです。外に行く時は必ずこのページだけ持って行くんだって。何故これが好きなのかはわからないんですよ。ただ、この絵本の中のあるページに共感してくれているんですね。
余談ではありますが、これの本は発売当時大変不評でね。日本の専門誌でもの凄く叩かれたんです(笑)。「語りの芸術である落語をこんなくだらないものにするとは何事だっ!」ということを、児童文学者たちに散々言われました。
林さんの絵のタッチは、いろいろなタッチがありますね?意図的に使い分けたりするのですか?
僕は色々なタッチがあると言われる方でしょうね。僕はそれで構わないと思っているんです。自分で良いと思ってやっているんだからね。結構無責任ですね(笑)。「本当の自分と、人から見た自分と、自分が思っている自分と3つある」って言うでしょ。考えてみれば本当の自分というのはわからないんですよね。そうするとやりたいと思った事は、何やってもいいんじゃないかなって。どうせあいまいな事して、わかんなくて終わっちゃうんだから。
絵は描いているとどんどん変化していくものなんですよ。「一生かかって子供の絵が描けるようになった」とピカソが言っていますよね。僕もあんな自由に素晴らしい絵が、いつか描けたらいいなとは思いますね。
色は工夫すると面白いんですよ。工夫しすぎると仕事が来なくなりますけどね(笑)。日常的にいろんなことを実験しますよ。たとえば、名画なんかを見ていて「色が面白い!」と感じるものは、配色をそっくりそのまま自分の絵に吸収しちゃう。でも、いくら真似しても並べて見ると全然違う絵なんです。それは色の面積のパーセンテージが違うからなんですよ。ちょっとした微妙な違いで完全に雰囲気が変わっちゃうんですね。
幸い僕は落書きするのが好きで、時間が空けばいつも落書きをしています。それはまだ続けられそうで、それが続けられる限りイラストレーターとしてやっていこうかなという…そんなに思っていますね。
林 恭三(はやし きょうぞう) Hayashi Kyozo

1939年、名古屋生れ、中国で敗戦をむかえる。
1958年名古屋市立工芸高等学校卒業。
1963年マサヤスタジオ退社後以後フリー。
大人物の雑誌、広告関係のイラストレーションで活躍。粘土を使った立体イラストレーションを、技法の一つとして日本のイラストレーション界に定着させる。1973年絵本「あたま山」ポプラ社/1981年絵本「かさじぞう」公文数学研究センター/1982年絵本「ゆみたろう」講談社/1984年作品集「人形家族」グラフィック社/1986年絵本「みんなでわらった」福音館書店/1989年絵本「ぼくおなかがぺっこぺこ」福音館書店・作品集「クレイイラストレ-ション・林恭三作品集」グラフィック社/1990年絵本文庫「お電話倶楽部」筑摩書房/1991年絵本「サンタの国へのふしぎなたび」ポプラ社/1992年絵本「月夜のしっぽ」架空社、などあり。